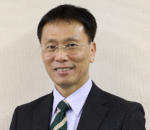Hey!guys.
Swatchです。
最近、通訳官時代のことを良く思い出します。
30年も前の話ですが、頭の中にその時の状況が浮かんできます。在京の各国大使館の武官との交流の仕事をしていたころのことです。
思い出に残っているのは、英語表現の深さを知った体験でした。
英国大使館の武官とイベントのスケジュール調整をしているときだったと思います。時間刻みのスケジュールをこなしていた武官に何気なく聞いた質問の答えが良くわかりませんでした。
「多くの人と会うのは大変でしょう」
と聞いたところ、
“I’ve got to meet a different people”
(いろいろな人に会わなければならない)
と武官はつぶやきました。
まあ、そうなんだろうなと思い、
“You have to”
(マストだよね)
と返したら、とんでもない答えが返ってきました。
<英国大使館の陸軍武官が言った言葉>
英国大使館の武官は、過密なスケジュールの中で、様々な人と会うことが仕事でした。
Swatchが、
“You have to meet a lot of people everyday”
(毎日、多くの人と会わなければならないですね)
と聞いたところ、、、
“I don’t have to. I get to!”
と返ってきました。
一瞬、意味が分からず、きょとんとしていると、武官は微笑みながら、次のように説明してくれました。
“I don’t have to meet people ”
(人と会わなければならないということじゃない)
と言った後に、
“I get to meet people”
と付け加えた。
受験英語では。
“get to do”は、「~するようになる」という意味で覚えていました。
とすれば、「人と会うようになる」。
まとめると、「人と会わなければならないのではなく、人と会うようになる」ということ?
何か意味がしっくりこない。
おもむろに電子辞書に手を伸ばした。
当時の電子辞書は、B5サイズの大きさで、外出の際には、いつも電子辞書を携えていた。
“get to do”を引いていると、「機会がある」と出ていた。
Swatchが辞書をのぞき込んで表情を変えたのを察したかのように武官は、
”I get to meet a lot of people at the Ambassy”
と付け加えてくれた。
「大使館で多くの人と会う機会がある」
ということだ。
つまり、仕事として、「会わなければならないということではなく、多くの人と会う機会がある」と発言してることが理解できた。
<I get to meetで伝えることができる気持ち>
職場で早速、通訳仲間に聞いてみたが、“I get to meet a lot of people”は、咄嗟に思いつかない表現だとことで一致した。
今考えてみると、この体験がSwatchの英語の学習の原点ように感じる。
英語のフレーズが正しいかどうかではなく、ネイティヴが持っているニュアンスを感じたいのだ。
そう考えると、学習意欲がむくむくと湧いてくる。
誰かに聞いてみたいという欲望がつのる。
ということで、在日米陸軍の知り合いの上級曹長に連絡してみる。
連絡と言っても、メールのやり取りをするわけではなく、事務所の電話での連絡である。
当時のことを思い出せば、携帯電話は発売されたばかりで、ティッシュ箱を二つ重ねたぐらいの大きさで、重量もかなりあった。個人では買うことも、使用することもできない時代だった。
1990年代は、インターネットもほとんど普及しておらず、連絡手段は、オフィスにある電話のみだったのだ。今のように携帯ですぐに連絡が取れるのではなく、連絡が取りにくいということだ。
やっとのことで連絡が取れ、“I get to meet people”の表現を上級曹長に尋ねた。
上級曹長は、米陸軍大学のアカデミーを卒業しており、リーダーとしての話し方のプロである。
そのフレーズを耳にしたいきさつを話し、説明を求めた。
上級曹長は、英国大使館の大佐の気持ちを次のように語ってくれた。
“I don’t have to meet”
(会わなくてはならない、ことはない。)
というフレーズには、人と会うことが義務ではないことを強調している。
それに続く“I get to!”の前ぶりのようなものだ。
“I get to meet a lot of people“は、ニュアンスが分からないだろうが、「人に会うという機会(opportunity)を得られたことに、感謝したり、それを光栄だと思っていることなんだ。
だから、人に会わなければならないという義務感ではなく、人に会える機会を持てる素晴らしさとか、その感動を伝えたいということだと説明してくれた。
大使館の大佐は、きっと彼の仕事が大変気に入っていて、多くの日本人と会えることが素晴らしいと考えているんだと思うと感想をくれた。
<Opportunity を chance に代え、縁をえること>
機会(opportunity)は、偶然に与えられた時間という概念が強いが、その時間を意味あるものととらえて、好機(chance)に代えられる瞬間が人生には多くあります。
時間を意識すること、それがかけがえのないものであることを意識することで、時間は様々なchance に形を変えてくれます。
英国武官の多忙なスケジュールの中で、ただ人と会うだけに終わらず、素晴らしい出会いの時という考えをすれば、感謝がうまれ、時にはその人に出会ったことで感動を覚えることもあります。
30年前のSwatchは、英語のフレーズである“I get to meet people”に出会ったことことで、英語に関する学習の仕方が変化しました。
さらに、英語の表現力の多様さ、深さを知るようになりました。
そのフレーズを通して、人との出会いの大切さも気が付くことができたことは、それからの人生を変える大きなきっかけとなりました。
人と出会うこと、それは偶然ではなく必然であり、そこに必ず意味があります。その意味をしっかりと考えるだけで、単なる Opportunity が Chance に代わっていくことを数多く体験しました。
Opportunity を Chance に代えることは、つまり、人との縁をつなぐことです。これからも、一人ひとりの出会いを大切にし、縁を結んでいけたらと考えています。
あなたともこのコラムを通じて、なにがしかの縁が得られれば素晴らしいと考えています。
これからもよろしくお願い致します。
執筆家・英語教育・生涯教育実践者
大学から防衛庁・自衛隊に入隊。10年間のサバイバル訓練から人間の生について考え、平和的な生き方を模索し離職を決断する。時を同じくして米国国費留学候補者に選考され、留学を決意。米国陸軍大学機関留学後、平和を構築するのは、戦いを挑むことではなく、平和を希求することから始まると考えなおす。多くの人との交流から、「学習することによって人は成長し、新たなことにチャレンジする機会を与えられること」を実感する。
「人生に失敗はなく、すべてのことには意味があり導かれていく」を信念として、執筆活動を継続している。防衛省関連紙の英会話連載は、1994年1月から掲載を開始し、タモリのトリビアの泉に取り上げられ話題となる。月刊誌には英会話及び米軍情報を掲載し、今年で35年になる。学びによる成長を信念として、生涯学習を実践し、在隊中に放送大学大学院入学し、「防衛省・自衛隊の援護支援態勢についてー米・英・独・仏・韓国陸軍との比較―」で修士号を取得、優秀論文として認められ、それが縁で定年退官後、大規模大学本部キャリアセンターに再就職する。
修士論文で提案した教育の多様化と個人の尊重との考えから、選抜された学生に対してのキャリア教育、アカデミック・アドバイジングを通じて、キャリアセンターに新機軸の支援態勢を作り上げ、国家公務員総合職・地方上級職、公立学校教員合格率を引き上げ高く評価される。特に学生の個性を尊重した親身のアドバイスには、学部からの要求が高く、就職セミナーの講師、英語指導力を活かした公務員志望者TOEIC セミナーなどの講師を務めるなど、大学職員の域にとどまらぬ行動力と企画力で学生支援と教員と職員の協働に新たな方向性をしめした。
生涯教育の実践者として、2020年3月まで東京大学大学院教育研究科大学経営・政策コース博士課程後期に通学し、最年長学生として就学した。博士論文「米軍大学における高等教育制度について」(仮題)を鋭意執筆中である。
ワインをこよなく愛し、コレクターでもある。無農薬・有機栽培・天日干し玄米を中心に、アワ、ヒエ、キビ、黒米、ハト麦、そばを配合した玄米食を中心にした健康管理により、痛風及び高脂質血症を克服し、さらに米軍式のフィットネストレーニング(米陸軍のフィットネストレーナの有資格者)で筋力と体形を維持している。趣味はクラッシック音楽及びバレエ鑑賞。
Facebook
https://www.facebook.com/takeru.suwa.7/
※友達申請いただく際「World Lifeで見ました」と一言コメント頂けますでしょうか。よろしくお願いします。