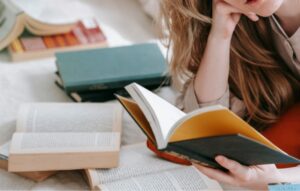Hi!
火曜日のJiroです。
先日、オッ!という体験が二つ。
一つ目は、「日経Asia」(英語の記事サイト)のKurzweil氏の新予言の記事を見つけた時。
彼は、2045年にAIが人知を超える、という予測で有名なコンピュータ研究者。今度は「2032は人が『不死になる』年と予言したらしいのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平均寿命は今一年に3か月程伸びているが、その伸びはさらに加速し、7年後には一年に1年以上になる。すると人間が一年生きる間に寿命の方もそれ以上延びる。結果として、誰も平均寿命に追いつけず一種の「死ねなくなる」状態になると言える。
(勿論人間は生身だから不死身になるわけではない。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ー正直、まてよ、と私は思いました。
そんなに安々と死を克服できるのだろうか。理由は二つ。
1つは平均寿命について。平均寿命は統計的にその年齢の人が半数亡くなる年。平均寿命が伸びていっても、それまでに半数の人が亡くなるという、途中で多くの人が亡くなる事実は変わらないのではないか。
2つは、仮に老化では死なないとしても、戦争や災害などで命を落とす可能性は残ること。世界が安全だという保障はどこにもありません。逆に事故・災害・殺人等で膨大な人が亡くなる未来になるかもしれません。
そんな記事を読んだほんの数日後、二つ目の「オッ!」がありました。
それは、小説家 Italo Calvino が収集した「イタリア民話集」を原語で読んでいた時のことです。
なんとそこに「誰も死なない国」という民話を見つけたのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ある男が「誰も死なない国」を求めて旅をし、ようやく辿り着く。
しかし何年も暮らすうち、残してきた家族や身内が気になりだし、故郷に戻ることを許されるが、条件がひとつ。それは「絶対に馬から降りないこと」。
馬に乗って行く先々、何もかも変貌し、知人の消息など皆目見当がつかない。
(皆もうとうに亡くなったんだろう)と諦めた帰路、荷車の傍に一人の男が。泥濘に車輪が嵌り動けず、助けて欲しいと言われるが、馬から降りられない、と断る。
しかし一人ぼっちで日暮れも近いと訴え続ける男に同情し、(完全に馬から降りなければいいだろう)と一歩地面に足をつけた瞬間、その男の表情が一変し掴みかかってきた。
“I have you at last!
(やっと捕まえた!)
Do you know who I am?
(私が誰か分かるか?)…
Now you’ve fallen into may hands,
(お前はもう私の手の中)
from which no one ever escapes”
(そこから誰も逃れられないのだ)
ーその男は死神だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この「誰も死なない国」を求める旅人は、誰の身にも置き換えられるのかもしれません。
誰もが、いつかは死ぬ運命だと知りつつ、「自分はまだ死なない」と思い、どこかで不死を夢見るけれど、死神は必ず執拗に追ってくる。思いもよらない場面で捕まる。
つまり「不死」を夢見る人間と、それを阻む「死」の存在。
未来の予測と、古い民話が、同じテーマを描いているように感じたのです。
そして現実の私たちはというと、平均寿命が伸びて「死ににくくなる」のは確か。英語で言えば、
It will be more and more difficult to die.
この「~するのが益々~になる」という表現は、英作文の時に役立つので、是非。
今回、Kurzweil / カーツワイルの未来予言と、イタリアの昔話を、英語とイタリア語で読んだことで、「死と不死」という普遍的なテーマが文化を超えて語られていると実感しました。
やはり外国語を読むことで、色々な情報を得ることが出来、世界が広がりますね。
See you soon!
Jiro
◯イタリア民話集 by Italo Calvino (英語版)
https://amzn.to/4mZjR02
私立学校に英語教師として勤務中、40代半ばに差し掛かったころ、荒れたクラスを立て直す策として、生徒に公言して英検1級に挑戦することを思い立つ。同様の挑戦を繰り返し、退職までに英検一級(検定連合会長賞)、TOEIC満点、国連英検SA級、フランス語一級、スペイン語一級(文科大臣賞)、ドイツ語一級、放送大学大学院修士号などの成果を得る。
アメリカで生徒への対応法を学ぶ為に研修(地銀の助成金)。最新の心理学に触れた。4都県での全発表、勤務校での教員への研修を英語で行う。現在も特別選抜クラスの授業を全て英語で行っている。「どうやって単語を覚えればいいですか?」という良くある質問に答える為、印欧祖語からの派生に基づく「生徒には見せたくない語源英単語集」を執筆中。完成間近。常日頃洋書の読破で様々な思考にふれているが、そうして得た発想の一つを生かして書いた論文がコロナ対策論文として最近入賞。賞品の牛肉に舌鼓をうっている。元英検面接委員