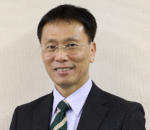Hey!guys.
月曜日のSwatchです。
前回記事で紹介した“I Quit Drinking”(お酒やめたの)という曲、聞いていただけたでしょうか。
酒好きの人には、逆に面白い歌詞ですよね。
さて、盆休みで、故郷で過ごされた人も多いと思いますが、Swatch も久しぶりに友人たちと旧交を温めました。
宴会などで、乾杯で、“Let’s enjoy!”「楽しみましょう」と言う人多いですね。
誰にでも通じて、発声の切れも良く、「これから飲むぞ~」という気持ちが出て、英語っぽくて、場が盛り上がります。
ただ、英語のネイティブが聞くと、少し変な感じに聞こえるって、知ってますか。
<Let’s enjoy!と言ったら笑われた>
日本では、言う方も聞く方も、あまり気にしませんが、この表現 “Let’s enjoy!”、実はネイティブに対していう場合は間違いです。
Swatch がある米軍とのパーティの通訳で,「楽しんでください」を”Let’s enjoy it!”と通訳したところ,日本人グループには,最後の”it”が聞き取れなかったらしく,その後のパーティでは
“Let’s enjoy! / レッツ・インジョイ”が飛び交うことに。それを聞くたびに,米軍人がニヤッと笑うので、都度
”Let’s enjoy the party!”
と“the party!”を付け足して大声で通訳していたことを思い出します。
というのも、“enjoy”は、文法的には、その直後に目的語を置く必要があります。
“Enjoy the game”(ゲームを楽しむ)、“Enjoy the night”(夜を楽しむ)といった感じです。
“Let’s enjoy ~!”は「~を楽しみましょう」ですから、「~」の部分なしに日本語でそのまま伝えたら、「を楽しみましょう」という感じに聞こえてしまい「何を楽しむのかわからない」から変なのです。
似たような文法を持つ語が、“love, visit, buy”などです。
“I love”だけでは意味が伝わらず、「あなたを愛している」であれば、“I love you”としなければなりません。
“I visit”も、どこを訪問したかが分からず、“I visited Kyoto”(京都に行った)で意味が通じます
“Let’s enjoy!”は、外国人の間では有名なジャパニーズ・イングリシュなので、日本に住んでいる外国人には意味が通じると思いますが、少し変な感じなのです。
乾杯の場合ですと、正しくは、
“Let’s enjoy drinking”
(飲むことを楽しみましょう)
になります。こなれた日本語にするなら、「楽しく飲みましょう」という感じですね。
先ほどの宴会の時に発声する「楽しみましょう」は、正しい表現にするとどうなるでしょうか。
“Let’s enjoy the party!”
(宴会を楽しみましょう)
“Let’s enjoy the evening!”
(今晩は楽しみましょう)
“Let’s enjoy our time!”
(みんなで楽しみましょう)
といった表現がぴったりだと思います。
英文法に従うだけで、不自然な英語が、自然に聞こえてきます。
<“Enjoy!”だけで通じるときもある?!>
enjoyに目的語をつけると、しっかりと伝わる文章になることはお話ししました。
自分自身が楽しんだ場合には、決まりがあります。
目的語を、myself(私自身)にすれば大丈夫です。
「楽しみました」は、文法的に考えると “I enjoyed myself”と表現します。
つまり、myself(自分自身)を、enjoyed(楽しんだ)ということです。
これは意味で考えるより、
“I enjoyed myself”
(楽しんだ)
と覚えておくと良いですね。
以上のことが、enjoyを使う時に基本形になります。
では、小題にあるように、“Enjoy!”だけで通じる場合を説明しましょう。
海外旅行で入国審査の手続きがおわり、最後に入国審査官から声をかけられたことはありませんか。
“Enjoy!”と言ってくれることがあります。(審査官によって違いますが。笑)
それは、誰かに対して、「何かを楽しんできてください」と言う場合に、例外的に「今からやることを楽しんでください」という意味の慣用表現として使うことがあります。
簡単に言えば、“Enjoy!”は、「楽しんでください」という慣用句として使われます。
答える場合には、
“I will, thank you! ”
(そうするわ。ありがとう)
が自然です。
文法にこだわりのある方は、以下の表現を参考にしてみてください。
“I’ll enjoy the trip in London! Thank you!”
(ロンドンの旅を楽しみます。ありがとう)
“I’ll enjoy myself here! Thanks!”
(これから現地で楽しみます。ありがとう)
目的語を英語でなかなか表現できないことってありがちですよね。
そんな時には、例文の“I enjoyed myself!”がお薦めです。
直訳すると、私自身を楽しんだですが、自分が楽しんだ=楽しかったという意味で使うことができます。
<Enjoyを使わず、従事した時間を説明する>
最後に、Enjoyを使わず、他の言葉で「楽しむ」を表現する方法もお伝えします。
仲間と一緒に楽しみたいときに、
“Let’s enjoy ourselves”
(みんなで楽しみましょう)
“Let’s enjoy the party!”
(宴会を楽しみましょう)
は、便利ですが、少しフォーマルな感じがします。
“I enjoyed myself”
(楽しみました)
“I’ll enjoy myself”
(楽しみます)
というのも、日常会話の中では、ちょっと硬い感じがします。
もっと軽く、楽な感じの表現で「楽しい感じ」を表現してみたいですね。
そんな時には、
“Let’s have fun!”
(楽しみましょう)
は、ワクワクする表現です。
人に対して、「楽しんでね」という時には、“Have fun!”と省略しても大丈夫です。
“fun”は、笑顔で楽しく過ごすということですので、ピッタリですね。
楽しいだけではなく、充実感がある時間を共有したいときには、“a good time”を使います。
“Let’s have a good time!”
友人と一緒に良い時間を過ごせそうですね。
さらに思い入れをもって時間を共有したいときには、“a great time”を使うと気持ちが伝わります。
“Let’s have a great time!”
で、仲間との時間を本当に実のあるものにしたい気持ちが伝わります。
これらの表現は、良い時間を共有することに気配りされているので、何かのイベントの時には、その場所やイベント名を付け加えることで、表現に臨場感が増します。
「ここで」、楽しい時間を共有しましょうという感じです。
イベントなどの場合は、
“Let’s have fun time at this great event”
(この素晴らしいイベントで、一緒に楽しい時間を共有しましょう)
と挨拶してみましょう。
素晴らしいイベント、一緒に、楽しい時間といったポジティブな言葉が並び、歯切れよく発声することで、場がグンと盛り上がると思います。
皆様も素晴らしい時間をお過ごしください。
追伸:
某国の外交官の友人が、
“I went to [Enjoy!] with my family last Friday night!”
と、六本木での武勇伝を話してくれたことがあります。
彼の説明から飲み屋の場所は推定できましたが、“Enjoy!”の意味が分からず確かめに行ったことがあります。説明を受けたお店の前においてある蛍光灯の掲示板に“Enjoy!”と小さく書かれているのをみて「ああ、これを店名と思ったんだな!」と納得しました。
執筆家・英語教育・生涯教育実践者
大学から防衛庁・自衛隊に入隊。10年間のサバイバル訓練から人間の生について考え、平和的な生き方を模索し離職を決断する。時を同じくして米国国費留学候補者に選考され、留学を決意。米国陸軍大学機関留学後、平和を構築するのは、戦いを挑むことではなく、平和を希求することから始まると考えなおす。多くの人との交流から、「学習することによって人は成長し、新たなことにチャレンジする機会を与えられること」を実感する。
「人生に失敗はなく、すべてのことには意味があり導かれていく」を信念として、執筆活動を継続している。防衛省関連紙の英会話連載は、1994年1月から掲載を開始し、タモリのトリビアの泉に取り上げられ話題となる。月刊誌には英会話及び米軍情報を掲載し、今年で35年になる。学びによる成長を信念として、生涯学習を実践し、在隊中に放送大学大学院入学し、「防衛省・自衛隊の援護支援態勢についてー米・英・独・仏・韓国陸軍との比較―」で修士号を取得、優秀論文として認められ、それが縁で定年退官後、大規模大学本部キャリアセンターに再就職する。
修士論文で提案した教育の多様化と個人の尊重との考えから、選抜された学生に対してのキャリア教育、アカデミック・アドバイジングを通じて、キャリアセンターに新機軸の支援態勢を作り上げ、国家公務員総合職・地方上級職、公立学校教員合格率を引き上げ高く評価される。特に学生の個性を尊重した親身のアドバイスには、学部からの要求が高く、就職セミナーの講師、英語指導力を活かした公務員志望者TOEIC セミナーなどの講師を務めるなど、大学職員の域にとどまらぬ行動力と企画力で学生支援と教員と職員の協働に新たな方向性をしめした。
生涯教育の実践者として、2020年3月まで東京大学大学院教育研究科大学経営・政策コース博士課程後期に通学し、最年長学生として就学した。博士論文「米軍大学における高等教育制度について」(仮題)を鋭意執筆中である。
ワインをこよなく愛し、コレクターでもある。無農薬・有機栽培・天日干し玄米を中心に、アワ、ヒエ、キビ、黒米、ハト麦、そばを配合した玄米食を中心にした健康管理により、痛風及び高脂質血症を克服し、さらに米軍式のフィットネストレーニング(米陸軍のフィットネストレーナの有資格者)で筋力と体形を維持している。趣味はクラッシック音楽及びバレエ鑑賞。
Facebook
https://www.facebook.com/takeru.suwa.7/
※友達申請いただく際「World Lifeで見ました」と一言コメント頂けますでしょうか。よろしくお願いします。