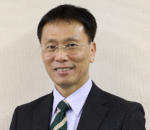Hey!guys.
月曜日のSwatchです。
日本人が習い始めで覚える英単語は、「サンキュー、オーケー、グッドモーニング」といった英単語ですね。
発音も日本語化しているので、す~と頭に入ってきます。ところが、“You are welcome!”は、どうでしたでしょうか。「どういたしまして」という意味がしっくりこない感じ。
単語ではなく、単語が3つもならんでいるし、自分のことを言っているのに、“you”で始まる。中学生のSwatchは、ちょっとしたカルチャーショックを感じました。
その結果、まる覚えで、“Thank you!”と言われたら自動的に“You are welcome!”と口から出ていた。いつも同じワンパターンの対応でした。
でも、それって、アメリカ人にとっては、少し変なんです。
<You are welcome!はかなりフォーマルな表現>
誰かに手助けをしてもらった時には、必ずお礼を言います。それが英語圏での常識です。
通常は、“Thank you!”と言えば大丈夫です。
ニュアンス的には、「ありがとうございます、どうもありがとう、感謝します」という感じ。
それに対応するには、丁寧に“You are welcome!”と応じるのが一番一般的。
“You are welcome!”は、フレーズがフルスペルされているので、フレーズ自体は、非常に丁寧に聞こえます。日本語では「どういたしまして」という感じです。
日本語で、普段「どういたしまして」は、あまり使わないですね。
非常にかしこまった感じがします。そのニュアンスが “You are welcome!” です。
日常的に使われる表現にするには、少し文を縮めて、“You’re welcome!” にします。
発音は、「ヨー・ウェルカム」といった感じです。なんとなくネイティヴポイ発音です。
これで、かなりカジュアルな表現に聞こえます。「どういたしまして」から、「どうもです!」という軽い感じになります。
と言っても、日常会話で親しい友人同士では、あまり使いません。“You’re welcome!”を、友人間で頻繁に使うと、友人との間になにがしかの壁を作る結果になります。
あるいは、気取った感じの性格に勘違いされることになるかもしれません。丁寧にするのは良いことですが、フレーズの重さを考えないと相手に誤解を与えることになります。
Swatchも若い頃、“Thank you!”と言われるたびに“You’re welcome”を使っていました。友人は、聞き慣れているので、また言ってるなという感じで受け流してくれていたと思います。
そもそも英語は、相手といかに会話を楽しむかという言語です。毎回、“You’re welcome!”を繰り返すSwatchは「出た出たワンパターンの返し」と笑われていたのかもしれません。
お礼に対する紋切型の会話は、聞いていても言われても面白くないです。何か自分の気持ちを刷っ繰と表す表現を準備しておくと会話がはずみますね。
<気軽に「どういたしまして」を伝える表現>
それでは、“Thank you!”とお礼を言われたときに、気軽にかつ自然に「どういたしまして」を伝える表現を3つ紹介します。
覚えておくと、一気にコミュニケーション能力が上がります。
「ありがとう」、「どういたしまして」で会話が終わってしまうのではなく、そこから気持ちの交流を始めることができます。
①
You bet!(ぜんぜん)
友人同士で非常によく使う表現が、“You bet!”です。「ユーベっ」と発音も簡単でキレがいいので、言いやすいですね。英語のフレーズは、早く言いやすいことが重要です。日本語で「夕べ」と言っても十分通じます。(笑) 意味は、「ぜんぜん気にしないで、もちろん、だいじょうぶだよ」という感じです。
“Thank you for your help”
(手伝ってくれてありがとう)
“You bet!”
(ぜんぜん)
②
Anytime!(いつでもどうぞ)
“Anytime”は、何か手伝うことがあれば、いつでも気軽に頼んでくださいと言う意味です。
「いつでも」言ってね、聞いてね、話してね!という意味です。時間やタイミングに関係なく、手助けや協力が必要ならば、いつでも言ってくださいと言う便利さがあります。
人に物を頼むときは、タイミングが気になりますが、そういった時間的に気になるところを、「いつでもいいいよ」と相手に伝えることができます。困った時には、時間に関係なくお願いするか感覚が伝わってきます。
“Thank you for picking me up at the station!”
(駅まで迎えに来てくれてありがとう)
“Anytime!”
(いつでもどうぞ)
③
No problem!(問題ないよ)
相手にしてあげた行為に対して、「問題ないよ」というのに抵抗がある年代もあります。年配のアメリカ人は、少し敬遠するフレーズかもしれません。若者の間では、そういったこだわりはなく、「問題ない、全然たいしたことではない、気にしないで」といった感覚で使われます。ネットなどのやり取りでは、“np”アブリビエーション(短縮形)を使ってやり取りをしています。No Problem の頭文字を2つ“np”と並べただけの略字です。
若者の間では、英語でも句読点を付けるのは堅苦しく感じられるそうです。
“Thanks!”
(ありがとう)
“np”
(問題ないよ)
ラインなどで使えそうですね。
<相手に心や感情を伝える表現>
カジュアルな表現を紹介しましたが、自分の気持ちや感情をしっかりと伝える表現もチェックしておきたいですね。これも 紹介しましょう。
①
Don’t mention it! ( どういたしたしまして)
“Don’t mention it!”は、直訳すれば、「そんなこと言わなくていいよ」ですが、お礼に対しての返答「どういたしまして」に使われます。カジュアルな場面からフォーマルな場面まで幅広く使えます。原意が、「そんなこと言わなくてよい」ですので、自分の気持ちを表す表現を付け加えると良いコミュニケーションになります。
引っ越しなどの手伝いをして、相手からお礼をいわれたときに、“Don’t mention it!”の後に、
“It was no trouble at all”
(全然たいしたことじゃなかったよ)
と付け加えると、相手のために頑張った感と自分の気持ちがストレートに伝わります。
相手が残業していたときに、ちょっと手伝ってお礼を言われたときなどに、“Don’t’ mention it!”と前置きをし、
“I’m happy it helped”
(役に立ったら嬉しいいよ)
と付け加えれば、相手をヘルプするポジティブな気持ちを伝えることができます。
②
Thank you! (こちらこそありがとうございます)
“Thank you!”と言われたら、すかさず“Thank you!”と切り返すこともできます。「Thank you返し」とも言います。意味は「ありがとう」、「こちらこそありがとう」という会話になります。その場合、自分が切り返す“Thank you!”は、youにアクセントをつけて発音するのがポイントです。友達の間の、「ありがとう」、「こちらこそ」という感じの会話はもちろん、フォーマルな感じの会話でも十分使えます。
“Thank you for inviting me tonight!
(今夜はお招きありがとうございます)
“Thank you”
{いらしていただいて感謝しております}
イベントの主催者に招待のお礼を言った時に返ってきた短い“Thank you!”は、参加してくれた客への短いけれど、気持ちの入った一言になります。
“You are welcome”(どういたしまして)というフォーマルな表現だけでなく、お礼を言われたときに、多様な受け応えができると、コミュニケーションが広がります。
会話が弾むことで、人間関係が深まります。“Thank you!”ときたら、気の利いたフレーズで会話を楽しみましょう。
執筆家・英語教育・生涯教育実践者
大学から防衛庁・自衛隊に入隊。10年間のサバイバル訓練から人間の生について考え、平和的な生き方を模索し離職を決断する。時を同じくして米国国費留学候補者に選考され、留学を決意。米国陸軍大学機関留学後、平和を構築するのは、戦いを挑むことではなく、平和を希求することから始まると考えなおす。多くの人との交流から、「学習することによって人は成長し、新たなことにチャレンジする機会を与えられること」を実感する。
「人生に失敗はなく、すべてのことには意味があり導かれていく」を信念として、執筆活動を継続している。防衛省関連紙の英会話連載は、1994年1月から掲載を開始し、タモリのトリビアの泉に取り上げられ話題となる。月刊誌には英会話及び米軍情報を掲載し、今年で35年になる。学びによる成長を信念として、生涯学習を実践し、在隊中に放送大学大学院入学し、「防衛省・自衛隊の援護支援態勢についてー米・英・独・仏・韓国陸軍との比較―」で修士号を取得、優秀論文として認められ、それが縁で定年退官後、大規模大学本部キャリアセンターに再就職する。
修士論文で提案した教育の多様化と個人の尊重との考えから、選抜された学生に対してのキャリア教育、アカデミック・アドバイジングを通じて、キャリアセンターに新機軸の支援態勢を作り上げ、国家公務員総合職・地方上級職、公立学校教員合格率を引き上げ高く評価される。特に学生の個性を尊重した親身のアドバイスには、学部からの要求が高く、就職セミナーの講師、英語指導力を活かした公務員志望者TOEIC セミナーなどの講師を務めるなど、大学職員の域にとどまらぬ行動力と企画力で学生支援と教員と職員の協働に新たな方向性をしめした。
生涯教育の実践者として、2020年3月まで東京大学大学院教育研究科大学経営・政策コース博士課程後期に通学し、最年長学生として就学した。博士論文「米軍大学における高等教育制度について」(仮題)を鋭意執筆中である。
ワインをこよなく愛し、コレクターでもある。無農薬・有機栽培・天日干し玄米を中心に、アワ、ヒエ、キビ、黒米、ハト麦、そばを配合した玄米食を中心にした健康管理により、痛風及び高脂質血症を克服し、さらに米軍式のフィットネストレーニング(米陸軍のフィットネストレーナの有資格者)で筋力と体形を維持している。趣味はクラッシック音楽及びバレエ鑑賞。
Facebook
https://www.facebook.com/takeru.suwa.7/
※友達申請いただく際「World Lifeで見ました」と一言コメント頂けますでしょうか。よろしくお願いします。