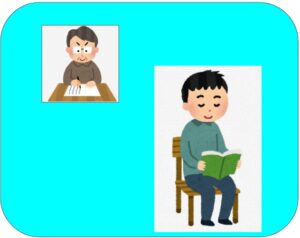Hi!
火曜のJiroです。
世界的ベストセラー『ホモ・デウス』の著者ユヴァル・ハラリ氏の新インタビューを久しぶりに観ました。
新著『Nexus』がテーマで、ニコラス・トンプソン(『The Atlantic』の元CEOでジャーナリスト)との対談形式で、AIや情報技術が人類社会に与える影響などについて議論されています。
ハラリ氏はネイティブの英語話者ではありませんが、正確な聞きやすい英語を話してくれるので、英語力アップの格好の教材でもあります。
今回のインタビューはとにかく面白く愉快。特に印象深かった3点をあなたとシェアしたいと思います。
それぞれ話されている大体の時間もお伝えしますので、是非参考に観てみてください。
1.情報の本質は「真実」でなく「繋がり」
(3分8秒~分かりやすい例)
一番はっとしたハラリ氏の指摘は、「情報は人を結びつけるのが本質」という点。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
…情報が真実かどうかは二の次。
大切なのは、情報が人同士を繋ぐ接着剤になることだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
接着剤になって繋ぐとは、例えば今、この記事を読んでいるあなたと、私が、見えない泡のような空間を共有する、という状態です。
私が(ああそうか!)と思ったのは、誰も彼もがSNS等に写真や動画をアップし出したのが不思議でたまらなかった(目立ちたがり屋ばかりだ、と反発するだけだったから)のですが、ハラリの視点で納得がいきました。
写真も動画も「情報」。
「情報」が人同士を結ばずにいられない、「情報」はシェアされずにはいられないのです。
英語で表現するなら
“Information can’t help but be shared!”
(情報はシェアされずにはいられない)
がまさにピッタリ。
「映え〜!」とか騒ぐ盛り上がりも、情報自体がそうさせると考えられる。
「情報」の本質が「真実を伝えること」ではないと言うハラリ氏….
考えてみれば確かに!趣味の団体も、会社も、国家も、何かの情報(ストーリーや約束事)によって成り立っています。でもそのストーリーがどうこうだより、結局グループがあることの方が大切ですよね。
2. 「オススメ」が持つ想像以上の力
(16分 30秒~)
もう一つの重要な指摘は、私達が情報の「オススメの力」を見くびっている点です。
スケールの大きな例をハラリはあげます。
新約聖書の27の文書がどうして決まったかという話。
「これ勧めよう」みたいな1,2回の会議で決まり、それがそのまんま1600年続いてるのですって。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
393年と397年の2回の会議で、司教や神学者達が「良き教徒は何を読むべきか」を決めた。マルコによる福音書から始まる現在の27書が正式に採用されたのだ。
そこでのお勧めの選択がいかに現代まで影を落としてきたか、簡単に想像できる。
まず採用の例。今も新約聖書27書の一つ。
テモテへの第一の手紙(2:11-12)
…“A woman should learn….full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority…
(女は…完全に従うべき。女が教え…権威を持つのを、私は許さない)
次に今の27書に採用されなかった『テクラの行伝』にはテクラという娘が布教したり、長年修道院のリーダーだったという内容がある。
The Acts of Paul and Theclaから
Thecla enlightened many.
(彼女は大勢を教化した)
Many led a monastic life with her.
(多くの女性が彼女と修道院生活を送った)
こんな内容が新約聖書に含まれていたら、歴史は変わったかもしれない。教会に神父プラス「神母」が生まれ、女性解放運動がもっと早く始まっていたかもしれない….
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
…なんと1,2回のオススメが、歴史の流れを決めちゃったというのです。
「オススメ」恐るべしでバカになんかできません。
ただ今、どうでしょうか?私も含めて、皆ネットで「オススメ」をただ楽しんでません?「オススメ」…あまりに無頓着ですよね。
偽情報に比べほぼ無警戒。怖いのは、どう警戒すべきか、私も含め実はよく分からないこと…..
よく分からない怖さって、本当は一番怖いのかもしれませんよね。
3. AIに煽られていないか
(1時間17分35秒~)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIは眠らない。食べない。疲れない。身体がないから。様々なプラットフォームやアプリは24時間365日休みなく動いている。真夜中だってAIは質問に答えてくれる。
これは言わば、毎日残業して会社に泊まり込み、飲まず食わずで働き続ける同僚がいるようなもの。休憩する自分が恥ずかしくなってしまう。
「煽られ兆候」は既に見られる。
例えば、よく耳にするこんな挨拶:
“I’m excited to see you here!”
(ここでお会いできてワクワクしています!)
「ワクワク」「興奮」は本当に良いことなのか?
常にテンション高めのハイな状態。目まぐるしい情報の嵐に好奇心を掻き立てられ、精神が常にオンになっている状態ではないか。
少し息をついた方が良いかもしれない。
“I’m bored to see you!” や “I’m relaxed to see you!” と言えたら良いのだが… (聴衆は爆笑)
さてハラリ氏のインタビュー、目から鱗のお話だったでしょうか?
Are you excited or bored to read this? That’ll be fine, both ways!
(読んでワクワク?それとものんびり?両方ともOKです!)
Until next week,
Jiro
追記:The acts of Paul and Thecla
https://web.archive.org/web/20120128042352/http://gbgm-umc.org/umw/corinthians/thecla.stm#10
<英語版>

私立学校に英語教師として勤務中、40代半ばに差し掛かったころ、荒れたクラスを立て直す策として、生徒に公言して英検1級に挑戦することを思い立つ。同様の挑戦を繰り返し、退職までに英検一級(検定連合会長賞)、TOEIC満点、国連英検SA級、フランス語一級、スペイン語一級(文科大臣賞)、ドイツ語一級、放送大学大学院修士号などの成果を得る。
アメリカで生徒への対応法を学ぶ為に研修(地銀の助成金)。最新の心理学に触れた。4都県での全発表、勤務校での教員への研修を英語で行う。現在も特別選抜クラスの授業を全て英語で行っている。「どうやって単語を覚えればいいですか?」という良くある質問に答える為、印欧祖語からの派生に基づく「生徒には見せたくない語源英単語集」を執筆中。完成間近。常日頃洋書の読破で様々な思考にふれているが、そうして得た発想の一つを生かして書いた論文がコロナ対策論文として最近入賞。賞品の牛肉に舌鼓をうっている。元英検面接委員