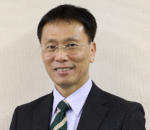100名以上のパーティ会場で主賓のアメリカ軍人と自衛隊高官の通訳を担当して通訳デビューした時の話。
10分程度のスピーチも最後の段階になり、締めの言葉を待った。ゲストは、米軍と自衛隊の交流の重要性を述べた後に、実際に自衛隊の演習に参加した時のエピソードを口にした。
「自衛隊の偽装の技術は素晴らしい。米軍も見倣わなければならない。」に続き、最後のきめのフレーズが誇らしげに発音された。
「のしのしゅ!」
場は静まり返った。Swatchの通訳を待っている。
頭が真っ白になった。「のしのしゅ」とは何か?!
逡巡していると、米軍の日本人妻が大声で言った。
「見えなけりゃ、撃たれないってことよ」
ここで、場内は大爆笑!
「のしのしゅ」は、“No see, no shoot!” だった。通訳デビューで、大恥かいた(笑)
しかし、陸幕副長(陸上自衛隊NO2)が、退席される際、Swatchに「素晴らしい通訳だった」とひとこと。涙が出るほど、嬉しかった。
自衛隊で学んだ「守破離」で「英語道」を
守破離(しゅはり)とは、武道、茶道や歌舞伎など修行において進化する状態をいいます。最初に、師匠の教えを守ることから始まり、習得できたらその型を破る。最終的には独自の型を生み出すというような過程(プロセス)を言い、この三段階の流れを、「守破離」と呼びます。
自衛隊には、「銃剣道」という武道が訓練科目として存在して、特に、陸上自衛隊の隊員には、必修の訓練科目なのです。銃剣とは、ライフル銃に短剣を装着した武器で、通常は、短剣を装着した銃を形どった木銃(もくじゅう)で、戦います。
その中で、上達のための心得として、「守破離」が教えられます。
まずは、基本の動作を確実に覚えるため、基本動作を徹底的に繰り返します。次に、基本的な動作に応用動作を加えて戦闘力を高め、最後に、そこから独自の技やstyleを見つけ出し、道を究めるということになります。
この「守破離」の概念で、私の「英語道」を振り返りました。
松本道弘先生の「英語道」
「英語道」は、英語会のレジェンド松本道弘先生(1940年生まれ、享年82歳)が提唱されました。松本先生は、海外渡航の経験もなく、独学で英語を学習し、アメリカ大使館同時通訳を経て、NHK教育テレビ「上級英会話」講師を務め、英語を志す者の憧れでした。
英語修得を、武道のように「道」を求め修行する姿になぞらえ、級から段へランキングで評価する「英語道」を提唱し、国内で高い英語力を目指す人達に大きな影響を与え続け、英語のエキスパートを数多く輩出されました。
Swatchも、そんな英語道に高校生の頃から挑戦した一人です。
【守】英語の修行
天狗の鼻をへし折られた中学3年生
英語道における「守」とは、基本単語、基本文法を覚えることです。
Swatchが、英語の基本の大切さに気が付いたのは、中学校3年生の頃。
英語の先生の物まねがうまく、発音が良いと言われて天狗になっていたSwatchに、「英語のテストの点数悪すぎ!」と事実を告げた、英語テストがクラスで一番のクラスメート。彼は、うまく発音できても、基本文法や単語を知らなくては意味がないと言った。
母の言葉が心に刺さった
帰宅して、英語の答案用紙を見つめていたSwatchに母が言った。
「あなたがどうでもいいと思っていることは、全部大事なこと。それが基本というもの。基本がなければ、何もまともにできない。」
心にしみた。
同級生と母のダブルパンチに、やる気が出てきたSwatchは、基本がなければ、何もまともにできないと胸に刻み、もっぱら音読しながら記憶していった。
変化があらわれたのは中3の3学期、英語の得意なクラスメートと成績が並んだ。
知る喜び、学ぶ喜びが生きがいに
英語の基本も充実し、知識も増えていき、知る喜び、学ぶ喜びが生きがいとなっていった。新聞で新しい英語のテキストを見つけると、出版社に注文して何週間も待った、楽しい時間。
インターネットですぐに知りたいことが見つかる時代ではなかった。そんな時に松本道場を知り、留学しなくても英語ペラペラにという夢が膨らんだ、高校・大学時代の幸せな英語生活だった。
【破】職業としての英語「英語バカという蔑称」
自衛隊での屈辱的な日々
防衛省・自衛隊に入隊して、訓練に勤しんだ。一日が終わり、自分の時間に自習室に行き、英語のテキストに目を通すが、激しい訓練による疲労で睡魔が襲う。
自習室に英語のテキストを持ち込んで居眠りしている馬鹿がいると噂が立つ。
英語バカは、英語が少しできるが、役に立たない隊員ということらしい。新人銃剣道大会入賞、体力検定1級、射撃49点/50点でも、役に立たない隊員と評価される。
その後も評価をされたこととは裏腹に、「英語バカ」が付いて回る。
バカがさなぎから蝶へ変態した瞬間
防衛省の英語学校に入学し、卒業後、防衛庁情報部隊に転勤することに。500名以上集合した朝礼で、転勤の挨拶をする。
「この度、東京の情報部隊で捕虜尋問(じんもん)係として勤務いたします」
英語バカが、蝶か蛾に見えたかはわからないが、バカというさなぎが変態した瞬間だった。
転勤後、通訳としての機会はまだまだ遠かったが、情報部隊での英語情報の量はけた違いであった。
毎日が英語学習の日々。英語の翻訳を通して、英語のニュアンス、米英の文化が頭に入ってくる。さらに、週一で英語通訳訓練がスケジュールされていた。米軍人から英会話を学べる素晴らしい環境があった。
六本木での実践英語道修行
防衛庁がまだ六本木、現在のミッドタウンにあったころ、Swatchの六本木での英語修業、実践英語道がはじまった。
当時の東京都港区は、100人中17名が外国人という高密度外国人の町だった。
Barで外国人に声をかけ、英会話を学んだ。弁当箱のような電子英語辞書をもち、新しい英語表現をメモした。
毎日が実践英会話、英語道場の修行場であった。様々な人種と英語で交流し、スタイルの違う英語に触れ、個性?なまり?とにかく、英語は生きているという実感を得た。
失敗を乗り越えた先にあったもの
間もなく、英語通訳の実践の機会が来た。(冒頭の通訳デビュー失敗エピソード)
その後、外国人要人訪問で、通訳を務めさせていただいた。それから執筆にも手を出し、防衛ホーム新聞社の英語教室の連載も今年で30年を超える。
防衛省内では、英語のスワッチと呼称されているが、場合によっては、「英語バカ」という評価や妬みに近いものが混じっていることもあったが、英語道へのモチベーションに変えた。
【離】「英語も出来るんですね」
「英語バカ」からの脱却
防衛省・自衛隊を定年時、再就職先は教育機関を希望した。そのため、放送大学大学院に進学し、教育発達プログラムコースに入院した。
心の中では、「英語バカ」からの脱却の試みの一つ。
修士論文、「米、英、独、仏、韓国の政府再就職支援態勢の比較を通して」を上梓し、それが縁で私立大学に入職した。
再就職後、大学院の担当教授3人に呼び出され、博士課程進学を勧められた。「就活のために、学位(修士)を取得しただけで、「研究する気持ちはない」ときっぱりとお断りした。
数度の説得で、翻意して、東大大学院の博士課程を受験。受験科目が英語の論文翻訳だったので、合格できたのだと思う。英語道のお陰だと実感した。
人生を変えた一言
東大大学院で最年長の学生となったので、好奇の目で見られたり、職員と間違われたりした珍事はたくさんあるが、思い出に残るエピソードがある。
アメリカの大学から招いた教授を囲む討論会に参加したときのこと。日ごろ研究しているテーマを教授にぶつけた。期待するコメントが返ってきた。研究文献も紹介してくれ、研究者として、素晴らしい時間だった。
討論会が終わった後、その場で参加した女子大学院生が、私に目を輝かせて言ったことは忘れることができない。
「諏訪さんって、英語も出来るんですね」
この一言で、私の人生から「英語バカ」というフレーズが外れ、どこかに飛んで行った。守破離の「離」の瞬間だった。
研究者という挑戦分野で、英語を武器(道具)として使った瞬間だったと思う。
新たなる英語道への挑戦
守破離は、そのあとの段階がある。離れた後に、自分のstyleを確立することである。
現在は、英語の実力を培い評価してくれた古巣の自衛隊で「スピーチとマナー技法」講座の講師として、年間授業を担当している。
英語学習で得た、知見と技術をもとに、メタ認知理論を駆使して、自衛隊リーダーのスピーチ能力とプレゼン力を向上させる取り組みに挑戦している。
近い将来は、守破離の基本に戻って、英会話を教えたいと考え始めている。
守破離は自己分析
今回は、私の人生と英語の関係を書いてみました。英語との関わりは半世紀にもなりますが、英語、また英語の学習はSwatchの人生に大きな影響を与えてきました。
半世紀という時代の流れは、現代には合わないことも多くありますが、Swatchは、振り返ることによって、自分が気が付かなこと人生の意味に気づき、人生のコンセプトが見つかりました。
英語に出会い、英語道にはまり、そして、守破離という人生のコンセプトに出会うというプロセスを書きました。
守破離は、ひとつの経験を段階を経て発展させていく過程そのものです。これは英語学習に限らず、あらゆる分野に当てはまる普遍的な成長の仕組みです。
そして「守破離」を考えることは、つまり自己分析なのです。それぞれの人が決める期間で振り返り、自己分析することで、次の段階に進むための何かを得ることができます。
その「何か」が具体的に何であるかは、読者の皆さん自身が感じ取るものです。私の英語道の体験が、皆さんにとって何らかの気づきや発見につながることを期待しています。
執筆家・英語教育・生涯教育実践者
大学から防衛庁・自衛隊に入隊。10年間のサバイバル訓練から人間の生について考え、平和的な生き方を模索し離職を決断する。時を同じくして米国国費留学候補者に選考され、留学を決意。米国陸軍大学機関留学後、平和を構築するのは、戦いを挑むことではなく、平和を希求することから始まると考えなおす。多くの人との交流から、「学習することによって人は成長し、新たなことにチャレンジする機会を与えられること」を実感する。
「人生に失敗はなく、すべてのことには意味があり導かれていく」を信念として、執筆活動を継続している。防衛省関連紙の英会話連載は、1994年1月から掲載を開始し、タモリのトリビアの泉に取り上げられ話題となる。月刊誌には英会話及び米軍情報を掲載し、今年で35年になる。学びによる成長を信念として、生涯学習を実践し、在隊中に放送大学大学院入学し、「防衛省・自衛隊の援護支援態勢についてー米・英・独・仏・韓国陸軍との比較―」で修士号を取得、優秀論文として認められ、それが縁で定年退官後、大規模大学本部キャリアセンターに再就職する。
修士論文で提案した教育の多様化と個人の尊重との考えから、選抜された学生に対してのキャリア教育、アカデミック・アドバイジングを通じて、キャリアセンターに新機軸の支援態勢を作り上げ、国家公務員総合職・地方上級職、公立学校教員合格率を引き上げ高く評価される。特に学生の個性を尊重した親身のアドバイスには、学部からの要求が高く、就職セミナーの講師、英語指導力を活かした公務員志望者TOEIC セミナーなどの講師を務めるなど、大学職員の域にとどまらぬ行動力と企画力で学生支援と教員と職員の協働に新たな方向性をしめした。
生涯教育の実践者として、2020年3月まで東京大学大学院教育研究科大学経営・政策コース博士課程後期に通学し、最年長学生として就学した。博士論文「米軍大学における高等教育制度について」(仮題)を鋭意執筆中である。
ワインをこよなく愛し、コレクターでもある。無農薬・有機栽培・天日干し玄米を中心に、アワ、ヒエ、キビ、黒米、ハト麦、そばを配合した玄米食を中心にした健康管理により、痛風及び高脂質血症を克服し、さらに米軍式のフィットネストレーニング(米陸軍のフィットネストレーナの有資格者)で筋力と体形を維持している。趣味はクラッシック音楽及びバレエ鑑賞。
Facebook
https://www.facebook.com/takeru.suwa.7/
※友達申請いただく際「World Lifeで見ました」と一言コメント頂けますでしょうか。よろしくお願いします。