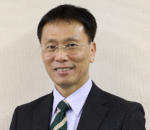Hey!guys.
Swatchです。
新政権で国会の討論が続いているが、答弁で「空中戦、地上戦」など、軍事用語が多用されていた。
Swatchの感覚からすれば、世の中変わったなという感じです。なぜかと言うと、日本の社会は、軍事に関わることに、非常に敏感で、文科省などは、20年前には、教育上ふさわしくないという理由で、軍事用語は使わないといっていた。
ところが、最近は、「strategy / ストラトジー」という言葉が使われています。軍事用語は使わないが原則であった文科省は、ストラテジーを、独特で微妙なアレンジ(翻訳)をして使っているのです。
<軍事用語を使う前に抑えておく基本>
文科省が軍事用語を使わないという風潮は、ある意味時代的には正しい判断だったと思います。
実際、軍事専門家、軍事評論家が、ビジネスと軍事を結び付けた著書を出しましたが、定着はしませんでした。
米国では、ハーバード大学ビジネススクールなどで軍事に関する事例研究で、一気に、軍事用語が経済用語へと変化し始めたのである。ビジネスで勝ち抜くために軍事戦略から学ぶ、という感じです。
軍事用語のビジネス界への転用は、米国で盛んになり、米国から日本へと入って来ました。それが、ビジネス用語と軍事用語との関係のルーツです。
ここで、外来語、ビジネス用語として、軍事用語を使用する場合、気を付けておくことがあります。
それは、日本における独特の使い方と軍事用語の本来の意味を理解しておくことなんです。
先ほど挙げた文科省のストラテジー(方略)を例に説明します。
ストラテジーを「戦略」として使うのは、軍事用語とビジネス用語では、共通です。
しかし、前述したように、文科省では、「戦略」と訳してはダメなのである。
文科省の定義に従い、「ストラテジー」を「方略」と使用しなければならない。厄介ですね。(笑)
そこがポイントなのです。軍事用語をなんとなく使ってしまうと、会話の齟齬を生じてしまう可能性がある。そこをしっかりと押さえておくことが、ビジネスパーソンとしての基本です。
<なぜ軍事用語が使われるのか>
軍事用語とビジネス用語の結びつきの基礎知識と、日本では、使う時に考えなくてはいけないポイントがありますよ!ということを説明しました。
それでは、なぜ軍事用語が、ビジネス用語として使われるのかをお話しします。
最初の理由は、簡単に、「カッコイイ」からです。
米空軍のパイロットが戦闘機にのり、出発の時に「Roger / ラジャー!」というシーンカッコいいですね。
それを意識してか、日本人でも日常会話の中で言う人を多く知っています。
次に、軍事用語は、「その言葉の持つ意味を、明確に定義しているので、的確に表現できる」からです。
これら二つの理由は、以前掲載しました「ラジャー!の本当の意味知ってる!?」を、再読ください。
二つ目の理由の、「定義が明白である」ということは、軍事作戦でも、ビジネスの戦略でも、非常に重要なことです。
言葉を聞いて、意味が不明確であれば、ものごとはうまくいきません。
Swatchが米陸軍将校から聞いた話です。
ロサンジェルスの街中で暴動が起きたとき、警察の部隊が道路を渡るときに、陸軍のリーダーに
“Cover(後方援護)”してほしい
と頼んだそうです。
そして、警察が前進した時に、いきなり陸軍の部隊が射撃を開始しました。
陸軍では、
“Cover”は、“射撃により敵の動きを制圧して、味方部隊を前進させること”
と陸軍将校は、説明してくれました。
米陸軍の笑い話なので、話半分としても、“Cover”という定義が、他の組織と違った場合は、想定外の結果を生むことになります。
そういった間違いが起こらないように、軍事用語はしっかりと定義がなされていることが、ビジネス界のニーズと一致し、多用されることになったのだと思います。
<ビジネスパーソンが考える会議の在り方>
ビジネス用語として、様々な軍事用語が採用されています。
前述した「空中戦(Air Combat)」などは、テレビへの出演やSNSによる情報発信し、効果を期待する行動のことです。
その中で、ビジネスパーソンが注目すべきなのが、今までの形にとらわれない会議の形態です。
文科省のホームページをのぞくと、様々な議題で審議が行われています。その中に、プロジェクトチーム、ワーキンググループと共に、軍事用語である「タスクフォース(Task Force)」 が使われています。
この数十年で、文科省も学んだのでしょう。独特の翻訳をつけるのではなく、そのままカタカナ書きにして、「タスクフォース」として会議の一種にしています。賢い!
実際、軍事用語として翻訳すれば、「任務部隊」になります。
定義は、軍で緊急性の高い事案(紛争など)に取り組むことを言い、特徴として、任務部隊で重要視されるのが、スピード感です。
自衛隊で最大規模のタスクフォースは、東北地震の際に編成された災統合任務部隊-東北(Joint Task Force-TOHOKU)でした。陸海空が統合(Joint)された形で運営され、被災地で活躍したことは記憶に新しいと思います。
タスクフォースの二つ目の特徴は、あくまでも臨時の編成であり、任務終了後は改組されるということです。
実際、Joint Task Force-TOHOKUは、防衛大臣の命により、2011年3月14日に編成され、同年7月1日に解組されています。
3つ目の特徴は、スピード感をもって、目的を実行するために、多方面、あるいは他部署から、実力者を抜擢して、特別に権限を与えて組織的に活動を後押しすることです。
そういった、緊急性のある会社の課題に対して、スピード感をもって、強力に会議を推し進めることができるタスクフォースを、ビジネスパーソンとして提案してみてはいかがでしょうか。
英語に堪能というだけでなく、最新のビジネスの取り組み方を取り入れてみる、あるいは提案してみる。素晴らしいビジネスパーソンですね。
今回は、軍事用語の日本へ入ってきたあらましから、軍事用語を使う前に押さえておくポイントを説明し、タスクフォースのような考え方が、あなたのビジネスに役に立つのではないかとお話ししました。
軍事用語を英語から学ぶことで、多くの視野を手に入れることができると思います。
執筆家・英語教育・生涯教育実践者
大学から防衛庁・自衛隊に入隊。10年間のサバイバル訓練から人間の生について考え、平和的な生き方を模索し離職を決断する。時を同じくして米国国費留学候補者に選考され、留学を決意。米国陸軍大学機関留学後、平和を構築するのは、戦いを挑むことではなく、平和を希求することから始まると考えなおす。多くの人との交流から、「学習することによって人は成長し、新たなことにチャレンジする機会を与えられること」を実感する。
「人生に失敗はなく、すべてのことには意味があり導かれていく」を信念として、執筆活動を継続している。防衛省関連紙の英会話連載は、1994年1月から掲載を開始し、タモリのトリビアの泉に取り上げられ話題となる。月刊誌には英会話及び米軍情報を掲載し、今年で35年になる。学びによる成長を信念として、生涯学習を実践し、在隊中に放送大学大学院入学し、「防衛省・自衛隊の援護支援態勢についてー米・英・独・仏・韓国陸軍との比較―」で修士号を取得、優秀論文として認められ、それが縁で定年退官後、大規模大学本部キャリアセンターに再就職する。
修士論文で提案した教育の多様化と個人の尊重との考えから、選抜された学生に対してのキャリア教育、アカデミック・アドバイジングを通じて、キャリアセンターに新機軸の支援態勢を作り上げ、国家公務員総合職・地方上級職、公立学校教員合格率を引き上げ高く評価される。特に学生の個性を尊重した親身のアドバイスには、学部からの要求が高く、就職セミナーの講師、英語指導力を活かした公務員志望者TOEIC セミナーなどの講師を務めるなど、大学職員の域にとどまらぬ行動力と企画力で学生支援と教員と職員の協働に新たな方向性をしめした。
生涯教育の実践者として、2020年3月まで東京大学大学院教育研究科大学経営・政策コース博士課程後期に通学し、最年長学生として就学した。博士論文「米軍大学における高等教育制度について」(仮題)を鋭意執筆中である。
ワインをこよなく愛し、コレクターでもある。無農薬・有機栽培・天日干し玄米を中心に、アワ、ヒエ、キビ、黒米、ハト麦、そばを配合した玄米食を中心にした健康管理により、痛風及び高脂質血症を克服し、さらに米軍式のフィットネストレーニング(米陸軍のフィットネストレーナの有資格者)で筋力と体形を維持している。趣味はクラッシック音楽及びバレエ鑑賞。
Facebook
https://www.facebook.com/takeru.suwa.7/
※友達申請いただく際「World Lifeで見ました」と一言コメント頂けますでしょうか。よろしくお願いします。