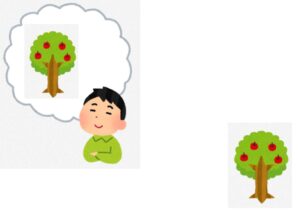Hi!
火曜日のJiroです。
Mrs. GREEN APPLE が巷で大人気ですね。
NHKの特集番組で気になり、私も聴いてみました。
そしたらすごい!
私の素人の耳にも声のコントロールのすごさが伝わってきました。
素晴らしいですね。
でも・・・言語オタクの私がもっと興味を惹かれたのはちょっと変わった?バンド名。
その中で、「green」「apple」の語源が気になり調べると、大人気の理由とつながるような意味にどり着いたんです!
ではまず「Green」。
祖先の古い古い単語DNAは、GHRA / グフラ(成長する)。
これが発音が少しづつ変化し、数千年の間に、様々な関連する英単語を生んだようです。
そんな同じDNA、GHRAをもつ単語をみていきたいと思います。
<「grand」 堂々と壮大な、立派な>
Do you have any grandsons or daughters?
(お孫さんはいらっしゃいますか?)
と、grandは英語では、grandfather/mother, grandson/daughterと使われます。でもフランス語でgrandと言うと普通に「大きい」。綴りも英語と(ほぼ)同じ。
これもDNAが、英語やフランス語等のヨーロッパ言語に共通なので分かることです。
GHRA(グフラ) 成長する→ 大きい → grand 堂々と壮大な、立派な
<「grass 」草>
Let’s eat lunch on the grass for a change.
(気分を変え外の芝生でお弁当を食べよう。)
最近、小松菜の根っこの部分だけを、水の入ったコップに入れといたら、よく伸びること!ぐんぐん成長し2週間ほどで葉っぱが7,8枚「収穫」できました。
太古の人々には、草の成長がはっきり見えたのかも。
DNAのGHRA「成長する」がgrass「草」と関係しているのも頷けるようです。
GHRA(グフラ) 成長する→ 成長する(草) → grass 草
<「green」 緑 緑色>
そして、発音や綴りが少し変化していますが、
green「緑いろ」が成長する草と関連しているのは本当にうってつけですね。
私は、Green Grassと聞いてすぐ思い出した曲があります。Tom Jonesの♪Green, Green Grass of Homeという曲です。あなたもどこかで聞いたことがあるかも。
こんな感じでゆったり始まります。
♪The old home town looks the same
(懐かしい家は(昔と)同じに見える)
As I step down from the train
(列車から私が降りる時に。)
And there to meet me is my Mama and Papa
(そしてそこで私を迎えてくれるのが母と父だ。)
Down the road I look and there runs Mary
道の向こうに目をやるとメアリーが走ってくる…(日本語は拙訳)
また緑には、若さとの連想があるのも当然な感じです。
例えばシェークスピアの詩の一節です。
Spring is near when green geese are breeding
(緑のガチョウが繁殖すれば春は近い)
などという表現があるようです。
GHRA(グフラ) 成長する→ 成長する(草の色)→ green 緑(色)
<grow (グロウ) 成長する>
Bamboo grows fast.
(竹は速く成長する。)
繰り返しになりますが、発音・綴りが少し変化しつつ「成長」のDNAから、growも生まれたようです。
但し英語ではgrowは「成長する」だけでなく「~を成長させる」という意味もあります。
My neighbor grows bamboo along the fence for privacy.
(隣人はプライバシーの為に垣根沿いに竹を育てている)
GHRA(グフラ) 成長する/させる→ grow (グロウ) 成長する 名詞 growth
<残念な「apple」の語源>
今度はappleの語源…と行きたいところですが、残念ながらはっきりしないようです。
「(一般的に)果実・実」という意味だったという説もあるそうです。
アダムとイブが食べたのは「禁断のリンゴ」と思われていますが、聖書を読んでみると何の果物かまでは書いてないようですから、ちょっと意外。
さて人気急上昇のMrs. GREEN APPLE ですが、英語好きな私には気がかりが一つ。
それは英語で歌うことが、もっとあっていいのではということです。私としては英語の分かる世界中のより多くの人に、Mrs. GREEN APPLE の良さを感じてもらいたいのです。
人気急上昇中の彼らのバンド名に「成長」を意味する単語「Green」が含まれているのも、どこか象徴的に感じられます。今後さらに「大きく成長」してほしいと願っています。
See you later,
Jiro
私立学校に英語教師として勤務中、40代半ばに差し掛かったころ、荒れたクラスを立て直す策として、生徒に公言して英検1級に挑戦することを思い立つ。同様の挑戦を繰り返し、退職までに英検一級(検定連合会長賞)、TOEIC満点、国連英検SA級、フランス語一級、スペイン語一級(文科大臣賞)、ドイツ語一級、放送大学大学院修士号などの成果を得る。
アメリカで生徒への対応法を学ぶ為に研修(地銀の助成金)。最新の心理学に触れた。4都県での全発表、勤務校での教員への研修を英語で行う。現在も特別選抜クラスの授業を全て英語で行っている。「どうやって単語を覚えればいいですか?」という良くある質問に答える為、印欧祖語からの派生に基づく「生徒には見せたくない語源英単語集」を執筆中。完成間近。常日頃洋書の読破で様々な思考にふれているが、そうして得た発想の一つを生かして書いた論文がコロナ対策論文として最近入賞。賞品の牛肉に舌鼓をうっている。元英検面接委員